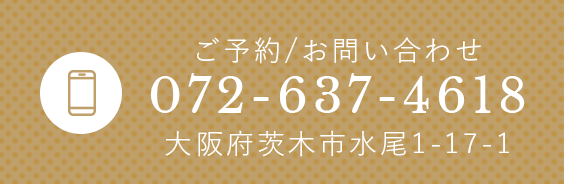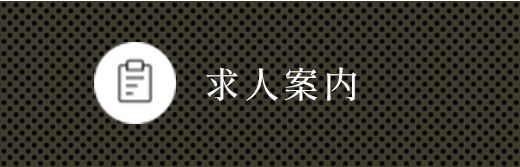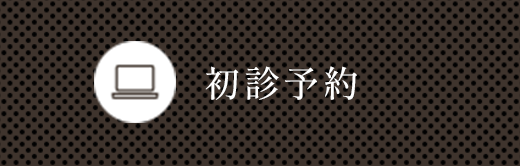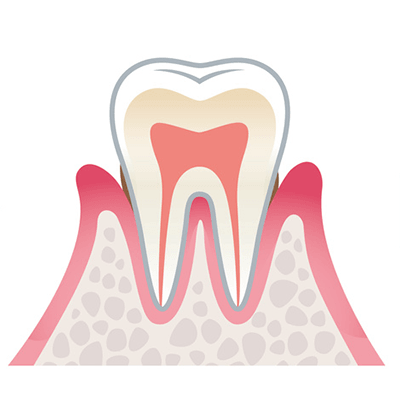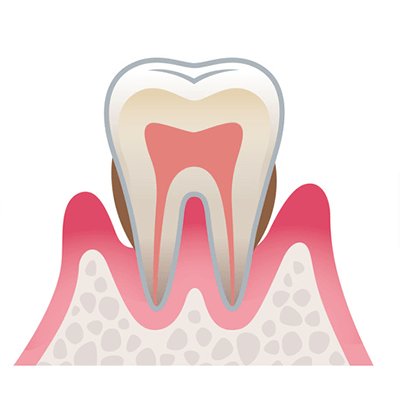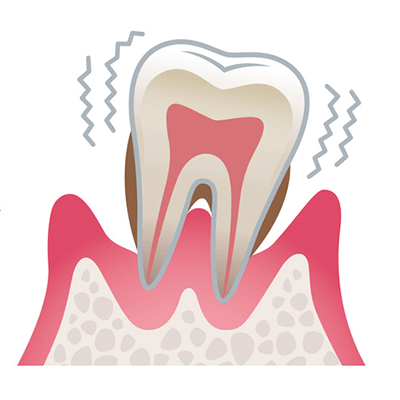プラーク(歯垢)
歯周病の主な原因は、歯と歯茎の間にたまるプラーク(歯垢)です。
プラークは、多くの種類の細菌が増殖してかたまりとなったもので、ブラッシングが不十分だったり、砂糖を過剰に摂取したりすると、細菌がネバネバとした物質を作り出し、バイオフィルムという粘膜性の膜を形成します。歯の表面のバイオフィルムは、毎日の歯みがきと定期的な歯科受診によってコントロールが可能ですが、歯と歯茎の間に深い歯周ポケットがあると十分にクリーニングできず、細菌が産生する毒素が歯周組織を刺激し、慢性的な炎症反応を引き起こします。これが歯周病と呼ばれる状態です。
プラークは取り除かなければ硬くなり、歯石という物質に変化して歯の表面に強固に付着します。歯石自体には病原性はありませんが、プラークの格好の住家となります。歯石はブラッシングだけでは取り除くことができません。
歯周病になりやすい状態(危険因子)
歯周病の直接の原因はプラークですが、口腔内の環境や生活習慣の中に、歯周病になりやすくなったり、悪化させたりする危険因子が潜んでいることが知られています。この因子が重複することで、歯周病の発症リスクが高まります。とくに口の中の清掃不良に加え、喫煙などの生活習慣、過度のストレス、体調不良による抵抗力の低下などが加わると危険です。
- プラークの中に歯周病の原因となる微生物(歯周病菌)が存在している
- 口内の清掃不良
- 喫煙
- プラークの付着量
- 歯ぎしり、歯の食いしばり、噛みしめ
- 不適合な歯冠や義歯
- 不規則な食習慣
- ストレス
- 免疫抑制剤の服用(免疫が低下している状態です)
- 部分的に歯がない
- 口で呼吸する習慣がある(粘膜や歯茎が乾燥すると、炎症が起こりやすくなります)
- 年齢
- 歯数
- 人種
- 糖尿病
- 遺伝
- 歯肉滲出液中の物質(歯肉から滲出する組織液で、その量は歯肉の炎症の程度と相関します)
- 白血球機能 など
歯周病予防は、適切な歯みがきでプラークを取り除くことが基本ですが、規則正しい生活習慣は、歯周病を寄せ付けないためにも大切です。